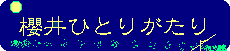「ふみ待つひと」
(六)
自分の身勝手を省みる余裕はなかった。とにかくこの地でたのみとする者は彼、矢口のほかにいないのだから。
川沿いの道をひきかえし、アーケード前の電話ボックスに入った。胸をさすり、乱れた息づかいをなだめてから彼の自宅の番号を押した。電話口には奥さんが出た。学生時代に何度か顔を合わせたこともあり、すぐに僕だと判ったらしい。
「まあ広瀬くん、おひさしぶり。このあいだウチのと飲んだんだって。チビの世話さえなきゃ、私もごいっしょできたのに残念ね」
「うん」
「そうそう、あれから連絡がつかないって気にしてるわよ。どうかしたの」
「ちょっとわけがあってね。それで心配かけたことは分かった。だから、ひとこと謝りたいんだ」
「そうか、じゃ呼んでくる。さっきお風呂から出たばかりから、ちょっと待ってて」
受話器の向こうで赤ん坊が泣いている。その声にかぶさるように、床を踏み鳴らす足音が近づいてきた。
「もしもし、広瀬か」
「ああ」
「今、どこにいるんだ」
「まだこっちに、久遠橋の近くにいる」
「ホテルには、とうにチェックアウトしたと言われるし、おまえの実家に電話したら、行方しれずで捜索願を出したって、お袋さんが泣いて話すじゃないか。まったく人さわがせな。いい齢こいて家出少年の真似ごとかよ」
「・・・・・・・・・・・・」
「だまってちゃ分からんぞ。おまえ、何を考えてるんだ」
「電話じゃ言えない。会ってそのわけを話したいんだ。いますぐここに来てくれないか」
「いくらなんでも、いますぐは無理だ。これから女房が風呂に入る。その間、おれが子供の面倒をみなくちゃならんからすこし待ってろ」
「すこしってどれくらいだ」
「三、四十分ってとこかな」
「そんなに待てない」たまらず僕は声を張りあげた。「いますぐでないとだめだ。おれはおれじゃなくなりかけている。いくらかでも自分がのこってるうちに話を聞いてもらいたいんだ」
「おい、またとんでもないことを」と言って、矢口は思い直したように一呼吸おいた。「よし、本当に切羽詰まった事情なら何をおいても駆けつけよう。かいつまんででもいい、この電話であらましを説明してみろ。こっちにだって心の準備が要るからな」
「・・・・・・おれのせいで」
「おまえのせいでどうした」
「あのひとが死んだ」
「えっ、だれが死んだって」
「この街でおれを待っていた女だ」
「ひょっとして、おまえが学生時代に付き合っていた娘、ええと・・・・・・そうだ、亜紀子のことか」
「ちがう、亜紀子じゃない、もっと前に生きわかれた女だ。けさ彼女に自分の正体をあきらかにした。ところが彼女は、おれを昔の恋人に成りすました偽ものと思いこんだ。そうだよ、やり方が悪かったんだ。きちんと罪をつぐなったうえで報せなきゃいけないのに、はやる気持ちにまかせていきなり真実をつきつけた。それがもとで弱りきっていた彼女の心がこわれてしまった」
「さっぱり意味がわからん。だから、その女はだれかと訊いてるだろ」
「ほら、いつも久遠橋に立っている長い髪の――」そこまで言いかけたところで、前ぶれなく咳がぶりかえした。矢口は、興奮のあまり僕がむせかえったと思ったようだ。「広瀬、頭を冷やせ。おまえ、言ってることがかなりおかしいぞ」と諭す口調で語りかけてくる。「でも事実だ。まちがっていない」と、僕はしゃがれた声をしぼりだす。
「いいや。そんな夢まぼろしを事実と思いこむこと自体、まちがってる。それくらいわからんのか」
「わからない。おれはぜったいにそのひとといっしょにいた。彼女がおれに宛てた手紙もたしかめた。いったいどこに――」夢まぼろしのまざる余地があるんだ、という文句がつなげない。また咳にさえぎられてしまう。
「ほんとに電話じゃどうしようもないな。すぐ行くから気をしっかり持て。いいか、ぜったいにそこを動くなよ」
電話は切られた。僕の手から力なく受話器が落ちた。
まちがってる、という友の言葉が耳にこだまする。自分はまちがっているのか。だとすれば、どこでどう道をえらびそこない、こんなにも深い狂気の峪におちいってしまったのか。
だめだ、咳が止まらない。酸欠で頭が痛くなってくる。いまにも額が爆ぜてしまいそうだ。「たすけてくれ」とうめいて、身体ごとガラスにもたれかかる。すると公園で聞いた女の声が、矢口の言葉を引きとって僕をさいなむ。
――そう、あなたはまちがっている。
なぜだ、 と僕は心でさからった。「あんたが、ここに戻るようそそのかしたんじゃないか。なぜいまさら、僕の行為を否定する」
――心がわりなさったのはあなたの方です。あれほどかたく誓っておきながら、最後の最後にきて、つぐないのつとめを放りだすとは。いえ、なによりいけないのは、あなたがあの方とともにすごした歳月を、夢まぼろしとうたがったそのことです。
「そう言われたって、僕は自分の正体さえ信用できなくなっている。本当のことが知りたい。でも彼女がいなくなった以上、それをたしかめる手だてはない。彼女の死で、僕の拠りどころすべてが失われてしまったんだ」
――あなたは外にとらえるかたちをもってしか、真偽のけじめをつけることはできないのですか。
「どういうことだ」
――これだけ言っても気づいていただけないようですね。すでにあなたは、時のうつろいをこえて変わることのない何かをとらえたはずなのに。思いだしてください、この街に来てふたたびあの方とめぐりあい、みずからの内に悟ったことを。いまはその事実をたよるしかありません。
・・・・・・あのひととの再会で悟ったこと、いくつもの夜を徹して考えたすえ、僕自身の心でとらえたこと。それは、不可視の領域を占める生前の記憶のうちに真の自分が生きつづける、という事実ではなかったか。なのに僕は、たとえほんのいっときにせよ、耳目をさわがす事象の変転にこころ惑わされ、真の自分が、彼女とともに在った時間を切りすてようとした。声は、それをあやまりと言いたいのか。
もういちど、しじまの奥に視た彼女の面影にたちもどる。目をとじて、この手でなぞる肩のなだらかさ、この指がすく髪のうるおいを盲人のようにたどってみる。そこへ再度、みちびきの問いが投げかけられる。
――正直な気持ちをあきらかにしてください。いまだにあの方が亡くなったと思っていますか。
「いや、あのひとは」
――その先をためらう必要はありません。こころひとつのあなたが言わんと欲すること、それだけをまことと信じ、いまここで言葉にすればよいのです。
うながしにしたがい「あのひとは生きている」と口にした。それだけで、あたらしい空気を呼吸するよろこびに膚がぴりぴりとふるえた。まちがいない、これこそ唯一、僕にとって否定しようのない真実だ。ガラスに映る自分の顔が、一転してはればれとした喜色をおびた。見えない声の主も同じく、会心の笑みを浮かべたはずだ。
「あのひとは生きている。いつまでも自分とともに在る」と唄うように繰りかえした。そして二度とゆるがぬ信念をいだいて、僕は電話ボックスのドアを押しひらいた。
車も人も通りから消えていた。物音はいっさい聴こえず、灯火ばかりが其処彼処に充ちていた。
白くかがやくビルのつらなりを高揚した気分であおぎ見た。橋灯から降りそそぐ銀光を浴びながら、かって彼女と交わした月夜の約束をかみしめた。いまその時が来たんだ、あのひとは死んではいない、ほんの一足先に新しい生へと歩みだしただけなのだ。それを悟ったからには、この世界でのどんな喪失も恐怖とはなりえない。
もはや僕は、この身体を喪うことを怖れない。この名前を捨てさることを怖れない。あるいは、この意識さえ無に帰することを怖れない。彼女とともに無形の生をいきる決意を胸に、寂然たる道をいそぐ。街道にも動くものの気配はいっさいない。軌道に停まった路面電車は、いましがた乗りすてられたかのように明るい客席をさらしている。
市街地をはなれると、急に景色の流れがはやくなった。家も木も標識も、白い糸をひきながら後方に去ってゆく。自分が駈けている自覚はなく、まるで風に乗ってはこばれているような感覚だ。しつこく胸を襲った咳からも解放され、呼吸はすっかり楽になっている。
そのまま川沿いの歩道に入り、芝生広場をかすめて船着場の跡にいたった。ちょうど例の石碑があったはずの場所に高灯篭が立っていて、その灯火の下にたたずむ人の姿がたしかめられた。白無垢に、同じく白の打掛けを羽織り、薄紅梅の角隠しを被った花嫁装束の女性だ。さらにもうひとり、きちんと紋服を着こなした婦人がその一歩うしろにひかえている。
「お待ちしておりました。ようやく正しい道を見いだしていただけましたね」と、紋服姿の婦人が言った。電話ボックスで聴いたのと同じ声だ。雲を被ったようにぼやけた顔のなか、ひかえめな紅の色だけが、笑みをふくんだ唇の動きを伝えている。
「これはいったい。僕のつぐないは果たしきれていないのに」
「いえ、素直に喜んでいただいてけっこうです。あなたがいちばん大切なことに気づいたそのときに、あやまちはみな帳消しとなりました」
「もしかして、あの電話のあとの……」
「そのとおり、あなたはいのちを投げだすよりつらい苦しみに堪え、この夜の、この場所にもどってこられた。お嬢さまのゆるしを得られないはずはありません」
「彼女をつれていってかまわないのか」
「その前に、二度とこの方をのこしてどこかへ行かないと誓っていただけます?」
「もちろん誓う」
「では、そのしるしに」
剃刀と、『倶會一處』の四文字が書きつけられた紙を婦人からわたされた。その誓詞の下には、すでに花嫁のものとおぼしき血判が捺してある。僕は躊躇なく親指の腹を傷つけて、ふたつのしるしが重なりあうように血の玉を押しあてた。婦人はうなずいてそれを引き取り、細く折りたたんだあと花嫁の懐にさし入れた。
「これでいっさい手ぬかりはなし。前のようなまちがいが起こるはずはありません。さ、出立のときが近づいてまいりました。お手をとりあって舟寄せの方へ」
僕は花嫁に歩みよった。その目元はまだ角隠しの蔭となっている。さし出した僕の手に、つつましくそろえた指が添えられた。
灯篭の灯に照らされた堤の石段をのぼりきった。足もとに驚くほど豊かな川相が広がった。石だらけだった河原は水中に没し、湾曲した岸に巾ひろく桟橋が架けわたしてある。僕らは堤を降りてその真ん中に立った。
ゆっくりと櫓を漕ぐ音が近づき、まもなく葦辺の陰から一艘の屋形舟があらわれた。艫にも舳にも水手の姿が見あたらない。なのに櫓の音は途絶えもせず、舷はくるいなく桟橋に寄せられた。僕らが乗りこむと、舟はひとりでに綱をほどいて桟橋をはなれた。岸から遠ざかるにつれ、突堤で見送る婦人の影も、灯篭の灯とともにしぼんで消えた。
舟は流れにまかせて川をくだった。頭上の月が、静かに僕と向き合う花嫁を照らしていた。それだけでじゅうぶん明るいはずなのに、両岸はすべて菫色のしじまにつつまれ、いまいる場所を知るすべはなかった。
「もとの世に未練はないかい」と問いかけた。
「あなたといっしょなら」待ちのぞんだ声とともに花嫁がおもてをあげた。その顔を間近に見さだめてから、僕はこたえのつづきをうながした。「僕といっしょなら?」
「どこへ行こうと極楽浄土。そして、月もこがねの花のよう」
彼女が指さす先、水面に金泥を流したように月影がゆれていた。雲の上と見まごうながめにおどろいて身を乗りだした勢いで舟がかたむき、舷ではじけたしぶきが僕の目に入った。
一瞬にして視界が真昼のかがやきに覆われた。彼女が言う通り、常夏の原を埋めつくす花のよう、無数のこがね色が手まねきしている。いくら目をぬぐっても、景色がもとにもどらない。やがて僕は、水底で月をながめる自分に気がついた。
苦しみも痛みもない。四肢がどこまでも伸びていく感覚に、みずからのすべてをゆだねている。そのまま、「いつまでもいっしょにいるから」という声を聴く。耳からではなく、内なる水の動きで僕はそのひびきをとらえた。
このとき僕は理解した。いくつもの生死をかさねたすえ、入江に流れこむ二筋の河のようにふたりが交ざりあったことを。そしてここまで自分をたぐりよせてきたいっさいの記憶は、ふたりを倶會一處のさだめにみちびく道しるべであったことを。「いつまでもいっしょにいる」僕らはあらためてひとつの声で誓いあう。
河口が近づいている。ほのかに潮の香りがただよいはじめた。語りつくせぬ想いは波にあずけ、しばし沖へといたるまで疲れたたましいを休めよう。ふみまつ日々のさみしさも、いまはむかしのこととなったのだから。
了
|